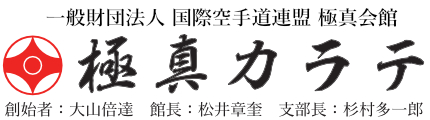4月15日火曜日
今回の審査で、少年部から2人昇段審査に挑戦しました。
1人は 秩父道場生、もう1人は熊谷道場生です。
熊谷道場は私の指導する道場ですから、成長は手に取るようにわかります。
秩父道場は坂本師範代の指導する道場です。
審査を受ける生徒の、普段の稽古の様子はあまり見たことがありません。
茶帯になるまでの昇級審査会や、今回の昇段審査の許可を出した後に、熊谷道場に稽古に来た時に見るくらいです。
それでも彼の成長は少ない接見で、自分の指導している生徒と同じように分かります。
もちろん坂本師範代に「彼頑張っていますか?」と聞くことはありましたが。
しかしそれよりも年に数回あった時の、挨拶、礼、目、かもし出す気で、しっかりと稽古を積んでいるのが分かるものです。
その気は、実際の稽古回数の多少に関わらず、空手修行に対する日常の心構えから出るものだと思います。
このことから、坂本師範代から昇段審査を受審させたいと相談があった時に、二つ返事で「もちろんです。」となった訳です。
熊谷道場の道場生は直接私が指導し、幼少の頃から成長を見てきた生徒です。
東松山道場の横尾先生にも多くの指導を受けています。
稽古は休む事なく、年間稽古回数は300回近く。
それを何年も続ける事により、確実な実力を身につけていきました。
試合出始めの頃は負け知らずでしたが、大会のランクが上がると悔し涙を流すことも度々。
それでも必ず稽古に来る強さがありました。
ここ2年くらいから空手に対する克己心も芽生え始め、稽古の取り組みも変わってきたと思います。
それからは道場での存在感も増し、リーダー的存在になっていきましたので、私としてはこれなら大丈夫と感じ、審査の半年ほど前に「黒帯に挑戦しなさい」となりました。
昇段は地道に稽古を重ねて、一定の実力が身に付くと本人の意思もありますが、道場内でも自然とそろそろとなります。
審査内容は前回記した通り、昇段に挑戦するに相応しい力を発揮しましたが、2人が初めから特別な才能があり、直ぐに強く上手くなった訳ではありません。
地道な稽古の賜物です。
空手は稽古を重ねれば、誰でも必ず上手くなり、強くなります。
運動神経、運動能力に左右されません。
松井館長が常々言われることは、「万人が持つ、人間の能力の凄いところは、反復した事は必ず身につくということ」
空手には万人が強く健康になるための、正しい形(かたち)を指し示す型(かた)があります。
これを反復することが大切です。
もちろん人によって稽古に当てられる時間が違いますので、実力が着くまでの時間に差が出ることはあります。
これもいずれ稽古が埋めていきます。
「昔から継続は力なり」と申しますが、稽古を重ねているとその事に心から気づかされます。
何事も正しく物事を積み重ねると、いずれ自他共に納得するものが身に付きます。
今回の審査でもまさにその事を感じさせられました。
空手を何も知らなかった子供達が、周りを唸らせ、組手が終われば感動の大きな拍手を生むようになるのですから。
武道の道は自身の意志で歩むもの。
やっとスタートラインに立ったばかりです。
心を引き締めて空手道を邁進して下さい。
このブログを書き始めた頃は、まだ審査結果の発表をしていませんでしたが、なかなか文章がまとまらず、本日のアップとなりました。
昨日月曜日に結果が発表され、2人とも黒帯合格となり、昇級審査の皆さんも無事全員合格となりました。
おめでとうございます!
これからも稽古を楽しみましょう!!
押忍。
✏️師範杉村。